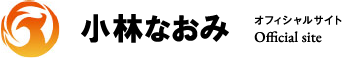「平成の大合併」で今から約20年前に市町が合併され、私が生まれ育った大川郡志度町はなくなった。
以降はさぬき市志度となっている。
月日は流れ、今度は私が通っていた高校が統合されなくなろうとしている。
近い将来、さぬき市内の3つの高校を統合して違う場所に校舎を新築する予定だそうだ。
加えて今月には約40年前に開校された大学のキャンパスが志度から高松駅前に移転した。
まちの衰退が加速するのではないかと懸念の声もちらほら聞こえる。
2023年9月17日の四国新聞(オンライン)には
・「共同通信が全国の自治体首長を対象に行った人口減少問題に関するアンケートで、86%が外国人材の受け入れを推進する必要があると答えた」
・「自治体が『消滅しかねない』との危機感を抱く首長は84%に上り、人口減に歯止めがかからず、自治体運営が厳しさを増す状況が浮かんだ」
・「香川県は知事と県内17市町長全員が危機感を抱いていると回答」
とある。
そもそも合併は自治体が消滅しないようにするものではなかったのか?
完全に逆効果になっていないか?
喫緊の課題を手っ取り早く解決するために、大量の外国人材を受け入れたり、外資系企業を誘致したりしたのでは長期的に見ると結果的に、先人たちが何百年と築いてきたまちの伝統や文化=独自のまちらしさを失うことにならないだろうか。
「自治体継続」のために外国人を受け入れた結果、本来のまちらしさを失い日本でなくなるのであればそれは本末転倒である。
北海道のニセコの例を挙げても、まちを気に入った外国人が不動産を次々と買収、移住し、そこでビジネスを展開した結果、まちの中では外国語が飛び交い日本語をほとんど耳にすることがない状態になっているそうだ。
このエリアで働けば時給がかなり良いため、地元の若者はここで働くことを選ぶらしいが、まちの機能としてのスーパーや小さな商店などでは働き手がいなくなって悲鳴が上がっている。
また、移民を招き入れることは容易かもしれないが、この方たちは人間なのだ。今の制度では不要になったからお帰りくださいということにはならない。増え続ける外国人労働者人口は2023年で200万人超。不法滞在者も増加している。
労働力として日本の経済に何十年か貢献し、そして、この人たちもいつか歳をとる。要介護になった時、現行のまま行けば、日本の社会保険を使うのだろう。その時の国民が負担する社会保険料は一体どうなっているのだろうか。また亡くなった場合は、宗教上の理由から火葬ではなく土葬にということもあり得る。その場合、墓地はどうするのだろうか。
将来起こりうる問題を想定してあらかじめ対策を打っておくべきなのだが、日本政府は外国人労働者を移民と定義せず、いわゆる「移民政策」をとらない。
このままだとこのツケは全て次世代そしてその次の世代にいくだろう。
そもそも日本の経済成長率が低迷し続けていることが若者の雇用不安定化→恋愛・結婚しない→少子化にも結びついていることを考えれば、日本政府が今すぐにすべきことは、積極財政と減税、そして非正規雇用を正規雇用にして若者が安心して結婚し、子供を産み育てる環境を整えることに尽きると思う。
経済活性化のために地方では企業誘致のことも耳にする。特に外資系の企業誘致に関しては、熊本県のTSMCの例、そしてお隣の愛媛県西条市丹原でのチャイナ企業による行政も絡んだ農地買収の例があるので、外国資本による水源地利用や土地買収のことも視野に入れておく必要がある。
自治体は水源地や農地が買収されたり、土地が汚染されることがないようにルール(規制)を設けておく必要があるだろう。
また肝心のその企業が生み出した利益がどれだけ日本社会、もっと言えば、そこで働く日本人労働者に還元されるのかも視野に入れる必要があるだろう。この30年間、日本人の賃金はほぼ横ばいだが、株主配当金は8倍になっている。
政策として日本人経営者や労働者に働いた分だけ利益が適正に分配される仕組みを作り、これまでの株主が所得を爆増させるような「株主資本主義」を根本から見直す必要がある。
地元住民の心と共にあり労働者が生きがいを感じて安心して働くことができ、末長く地元に貢献する企業なら誘致も前向きに検討できるのではないだろうか。